この記事にはアフィリエイト広告が含まれます。
「映像授業が気になるけど、中学生の子どもには早いかも...」こんな悩みを抱えてはいませんか?実際、中学生のお子様が映像授業を使って自主的に学習することが難しい場合もあります。そこでこの記事では、映像授業での学習が向いているお子様の特徴について解説します。塾講師として映像授業を活用してきて、映像授業を使いこなせる生徒・使いこなせない生徒を見てきたからこそ分かるリアルな視点です。ぜひ最後まで読んで、お子様が映像授業に向いているかを確認してみてください!
前回の記事では、中学生向け映像授業のメリット・デメリットについても解説しているので、合わせてご確認ください。
中学生でも映像授業は効果絶大
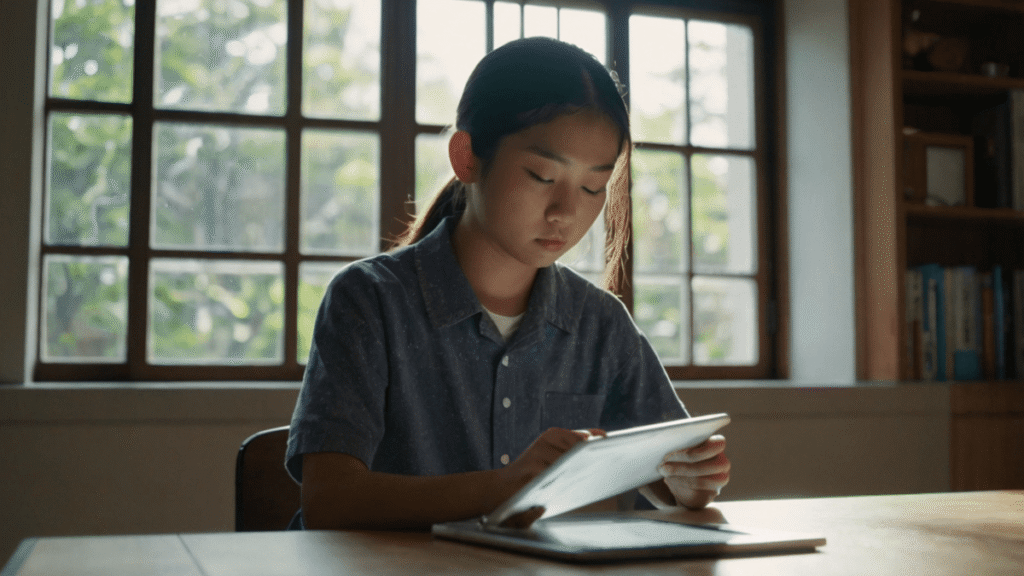
中学生に映像授業は早いのでは?と感じる方もいるかもしれませんが、実際には中学生でも映像授業の効果は絶大です。実際に私も講師時代には中学生に映像授業をおすすめしていました。
しかし、どんな中学生にでも映像授業が使いこなせるわけではありません。映像授業はきちんと使いこなすことで初めて効果を発揮します。
ここからは映像授業が向いている生徒・向いていない生徒の特長をそれぞれ紹介していきます。
映像授業が向いていないお子様の特徴

まず初めに、映像授業が向いていないお子様の特徴を紹介します。
自発的に勉強をする習慣がない
塾で提供される映像授業の場合は、塾の先生から指定されて受講することもありますが、個人で会員登録して受講するタイプの映像授業の場合、自発的に映像を見て勉強をする習慣が必要になります。
後で後で、と受講を後回しにしているうちに、気づけば何本も受講できていない授業があるというのも珍しくありません。
映像授業の効果を発揮するためには、自発的に学習をする姿勢が必要になります。
勉強に長時間集中できない
映像授業はPCやタブレット、スマートフォンで受講することが多いです。
これたの機器は気軽に勉強ができる一方で、SNSやゲームなどの誘惑も多いため、通知などで気が散って、勉強に集中できないお子様には向いていません。
一方で、映像授業受講中は通知をオフにする、プライベートで使用している端末とは分けるなどして対策を練ることも可能です。
分からない部分をそのままにしてしまう
映像授業のデメリットは、受講中に分からない内容があった時にその場で質問ができないことです。
そのため、分からない内容があった場合には、受講後学校の先生や塾の先生に質問して、内容を理解する姿勢が重要になります。
映像を見ただけで勉強をした気になってしまい、疑問点をそのままにしてしまうお子様は要注意です。
映像授業が向いているお子様の特徴
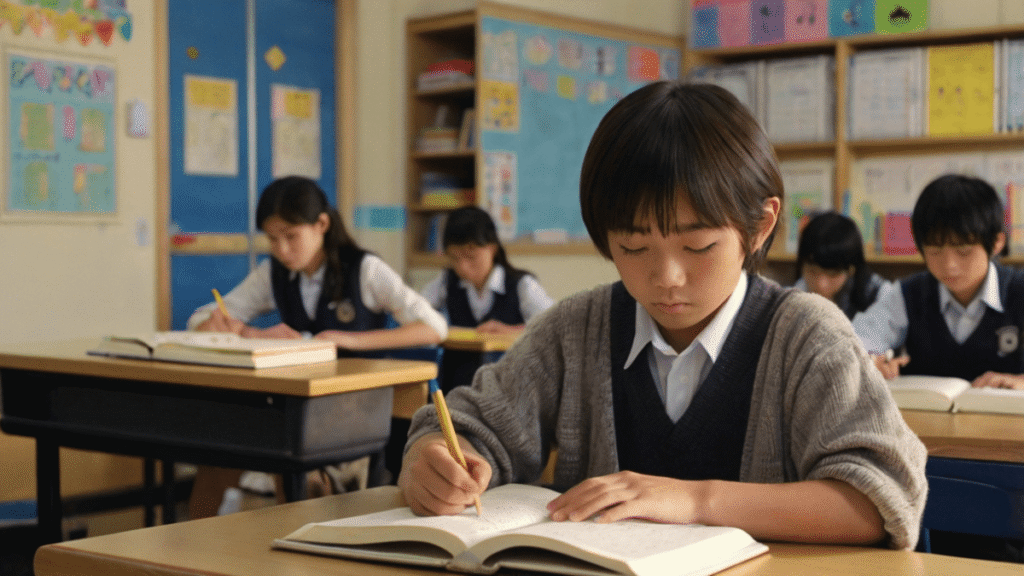
では逆に、映像授業が向いているお子様の特徴にはどのようなものがあるのでしょうか。
自分で計画的に勉強ができる
「次のテストまでにここまでの範囲を終わらせる」「1日に何個の授業を見る」などといったように、自分で計画的に学習ができるお子様は映像授業に向いています。
映像授業は個人での会員登録の場合、誰かに進捗を監視されるものではないので、自発的に学習する姿勢が必要です。
分からない内容は自発的に質問できる
上述の通り、映像授業は疑問点をすぐに質問できないので、受講中に疑問に感じた内容は、後から学校の先生や塾の先生に質問する姿勢が大切です。
分からない内容をほったらかしにせず、理解するまで質問ができるお子様は映像授業に向いています。
1回で内容を覚えるのが苦手
映像授業の利点は、何度でも見返すことができるところです。
そのため、「授業で話している内容は理解できるけど、時間が経つと忘れてしまう」「1回では覚えきれないけど、何回か説明を聞いているうちに覚えられる」というお子様には映像授業が向いています。
もちろん学校の先生や塾の先生も、何度でも教えてくれるはずですが、同じ内容を何度も質問することに気が引けてしまうお子様もいるかと思います。
「もう一度説明が聞きたい!」と感じた時に気軽に再生できるのは映像授業の大きなメリットです。
まとめ
今回は、映像授業が向いているお子様・向いていないお子様の特徴について解説しました。
- 使いこなすことができれば、中学生でも映像授業の効果は大きい
- 自発的に勉強をする習慣がないお子様や、勉強中に気が散ってしまいやすいお子様に映像授業は向いていない
- 自発的に勉強できるお子様や、1回で内容を覚えることが苦手なお子様は映像授業に向いている
もちろん、映像授業が向いていないお子様の特徴に該当していた場合でも、映像授業を導入することで勉強の習慣が変わることもあるので、「映像授業を受講するべきではない」と一概には言えません。
映像授業はしっかりと使いこなすことができれば、非常に便利な学習方法となるので、ぜひお子様とも相談して、導入を検討してみてください!

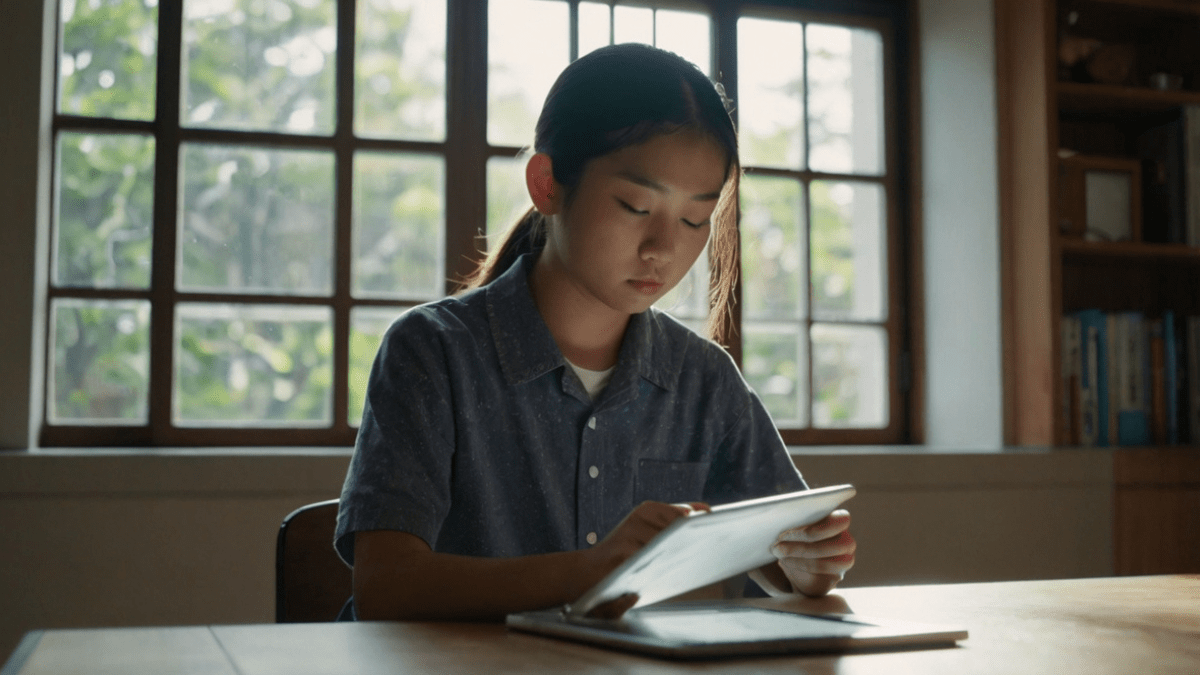
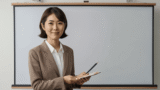


コメント